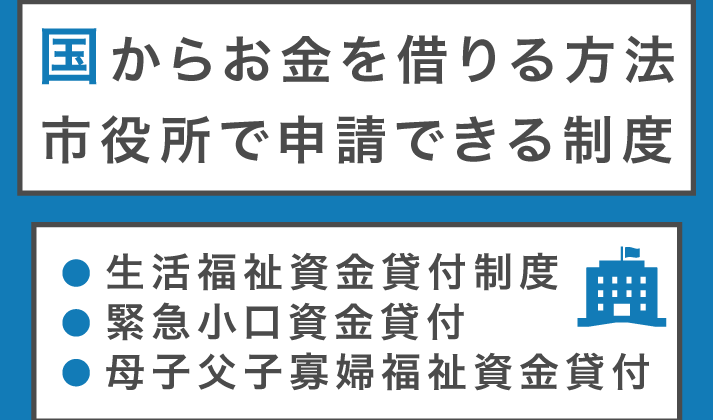
個人向け公的融資制度を利用すると、消費者金融や銀行カードローンから融資を断られた人でも、国からお金を借りることが可能です。
公的融資制度を管轄している厚生労働省は、貸金業者のように利息収益を得るのではなく、社会保障として国民の自立支援と救済を目的に融資を実施しています。
無職や低収入の人でも貸付対象になる個人向け公的融資制度の一覧は、以下のとおりです。
- 生活福祉資金貸付制度
- 緊急小口資金貸付
- 求職者支援資金融資制度
- 教育一般貸付
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
- 看護師等修学資金
- 臨時特例つなぎ資金貸付
上記の公的融資制度は無職でも貸付対象になるだけではなく、返済の負担を軽減できるよう無利子または3.0%以下の低金利で借り入れできるのが特徴になります。
ただし公的融資制度は国民が納付した税金を財源にしており、貸付対象として相応しい人物であるかを慎重に審査しているため、誰でも融資を受けられるわけではありません。
公的融資制度を利用するには、政府が基準を定めている低所得者世帯に該当して条件を満たす必要があります。
この記事で分かること
- 公的融資制度の審査に通過する条件は低所得者世帯であること
- 国からお金を借りるなら資金使途が幅広い生活福祉資金貸付制度が最適
- 即日で申し込める緊急小口資金貸付なら融資までの待ち時間が短い
- 居住する地域の社会福祉協議会で申し込みが完了する
この記事では、国からお金を借りる方法や個人向け公的融資制度の一覧を紹介しています。
公的融資制度を即日で申し込んで利用する方法も詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
国からお金を借りるなら生活福祉資金貸付制度を利用しよう
国からお金を借りるのなら、使用用途が幅広くて公的融資制度のなかでも利用しやすい生活福祉資金貸付制度を利用するのが最適です。
生活福祉資金貸付制度は以下の世帯を貸付対象にしており、低所得が原因で生活に困窮している人はもちろん、障害や高齢によって働けない人でも借り入れできます。
消費者金融や銀行カードローンで借り入れできない人でも貸付対象にしてもらえるうえ、利用目的に応じて種類が細かく分類されているのが特徴です。
利用目的や生活環境に応じて最適な借り入れができるよう、資金の種類ごとに借り入れできる内容も異なります。
生活福祉資金貸付制度の一覧は、以下のとおりです。
| 借り入れできる内容 | |
|---|---|
| 総合支援資金 | 生活費や住居費などにかかる費用 |
| 福祉資金 | 介護費用や冠婚葬祭の費用など、止むを得ない事情で必要なまとまったお金 |
| 教育支援資金 | 高校や大学の入学費用、授業料などの教育費 |
| 不動産担保型生活資金 | 現在の住居を担保とする高齢者世帯の生活費 |
なかでも総合支援資金は利用目的が幅広いだけではなく、無職でも借り入れできるほど貸付対象を幅広く設けています。
生活福祉資金貸付制度の申し込み先で悩んでいるのなら、最も利用率が高い総合支援資金を選んでおけば間違いないでしょう。
ここからは、ひとつずつ詳しく解説していきますので、参考にしてください。
総合支援資金は無職でも生活費の補填として一時的に融資を受けられる
総合支援資金は、失業や解雇などの理由で無職になった人でも生活費の補填として一時的に融資を受けられる制度です。
資金援助や就業支援を実施している制度で、生活再建できるようにサポートしてもらえるため、根本的な立て直しを図る目的でライフプランに関する相談を受けられます。
再就職への前向きな姿勢を見せることで、自立できる見込みがあると認められて審査に通過できます。
実際に管理人は失業中で生活が困窮している際、総合支援資金へ申し込んでおり、生活の立て直しに向けて懸命に働く旨を伝えたところ融資を受けられました。
総合支援資金は以下のように3種類に分類されており、利用する目的ごとに最適な支援をしてもらえます。
| 資金の種類 | 利用目的 | 貸付利子 |
|---|---|---|
| 生活支援資金 | 生活費全般 |
|
| 住宅入居費 | 引越し費用 | |
| 一時生活再建費 | 一時的な生活費 |
総合支援資金は保証人を立てると無利子で借りられることから、無駄な利息を支払う必要がありません。
保証人を立てられない場合でも1.5%の低金利な借り入れが可能で、利息の負担を軽減しながら利用できます。
総合支援資金でお金を借りるのなら、まずは資金使途の幅が広い生活支援資金の利用を検討しましょう。
生活支援費は光熱費や公共料金の支払いなどの生活費として借りられる
総合支援資金の生活支援費は、光熱費や公共料金の支払いといった生活費として借り入れできます。
生活が安定するまでに必要な費用であれば、以下のような幅広い用途に利用できるのが特徴です。
- 水道光熱費
- 公共料金の支払い
- 食費
- 引越し費用
- 学費
- 介護費
生活再建に必要な資金を3ヶ月間借り入れできるうえ、どうしても働けない事情がある場合は最長12ヶ月まで延長してもらえます。
ただし生活支援費は幅広い用途に利用できるものの、生活再建までの資金に限定されているため、娯楽費や債務の返済には利用できません。
申し込み時に資金使途を細かく確認されるだけではなく、他の用途で使用すると融資を打ち切られるケースもありますので注意しましょう。
借り入れする目的が引越し費用であれば、生活支援費と併用して住宅入居費を利用できます。
住居を借りる際に必要なお金が借りられる住宅入居費
住居入居費は、賃貸契約を結ぶために必要な費用を借り入れできる制度です。
例えば敷金礼金や不動産仲介料、前払い家賃などの支払いに役立てられます。
住宅入居費の限度額や貸付期間は、以下のとおりです。
| 貸付限度額 | 40万円以内 |
|---|---|
| 貸付期間 | 一括で貸し付け |
住居を借りる際の初期費用の相場は30〜40万円と高額になりますので、引越しのお金に困った際は一括で最高40万円を借りられる住居入居費を利用しましょう。
一時生活再建費は生活費で賄えない費用に利用できる
一時生活再建費は、日常費用で賄うことが困難な費用を借り入れできる制度です。
例えば就職に必要な技能を習得する経費や新住居の家具購入などの必要経費、滞納している公共料金の立て替えなどに活用されます。
返済できない借金があって債務整理をする際に必要な費用も、この制度で借り入れできます。
一時生活再建費の限度額や貸付期間は、以下のとおりです。
| 貸付限度額 | 60万円以内 |
|---|---|
| 貸付期間 | 一括で貸し付け |
最大60万円まで一括で借り入れできますので、多額の費用が必要な場合に最適です。
教育支援資金は低所得世帯の教育費をフォローする
教育支援資金は、低所得世帯の子供が高校や大学に就学するために必要な資金を貸し付ける制度です。
貸し付け対象となるのは就学する本人であり、同世帯の家族が連帯借受人となることによって無利子で借り入れが可能です。
連帯借受人とは?
借受者と連帯して、債務を負担する人のこと。
借受者が未成年者の場合は、原則保護者が連帯借受人になる。
据置期間は卒業後から6ヶ月で、就職して収入が安定するまで返済を待ってもらえるのが特徴です。
償還期間は20年と長く設定されており、余裕を持って返済できるように配慮されています。
教育支援資金は、用途別に2種類に分けられています。
就学するのに必要な経費を借りられる教育支援費
教育支援費は毎月の学費や通学定期代など、就学するのに必要な経費を分割で借りられる制度です。
自分が指定した口座に、以下の範囲の金額が毎月振り込まれます。
| 高校 | 高専 | 短大 | 大学 | |
|---|---|---|---|---|
| 貸付限度額 | 月3.5万円以内 | 月6万円以内 | 月6万円以内 | 月6.5万円以内 |
限度額は自己資金で対応できる額を除いた金額と定められており、卒業まで借り入れできます。
ただし一度決定された貸付額は変更できず、途中で増額を希望しても対応してもらえませんので注意してください。
入学時に必要な経費なら就学支度費
就学支度費は入学金や制服代、教材の購入費など入学時に必要な経費を借りられます。
最大50万円まで一括で借り入れできますが、納付期限を過ぎてしまった入学費などの経費は融資を受けられませんので注意してください。
学生がお金を借りる場合は教育支援資金の担当者に相談すると、日本学生支援機構による奨学金や生活困窮者自立支援制度の内容についても教えてもらえます。
申し込みは各地方自治体の社会福祉協議会となっていますので、進学費用で困った際は相談に行ってみましょう。
不動産担保型生活資金は高齢者の生活費を貸し付ける制度
不動産担保型生活資金は、65歳以上の高齢者が居住用不動産を担保にして生活費を借りられる制度です。
自宅に住み続けながらお金が借りられるため、住む場所を失う心配がありません。
自宅の評価額に応じて借り入れ額が決定し、本人が死亡後に自宅を売却して返済に充てるという仕組みになっています。
不動産担保型生活資金は、以下の2種類に分類されています。
| 内容 | |
|---|---|
| 不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯が利用可能 |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 要保護を受けた高齢者世帯が利用可能 |
連帯保証人を配偶者や子供などの推定相続人の中から選ぶ必要がありますが、要保護世帯の場合は不要です。
要保護世帯とは?
生活保護が必要であると各市区町村が認めた世帯のこと。
不動産担保型生活資金のそれぞれの貸付限度額は、以下のとおりです。
| 貸付限度額(総額) | 毎月の貸付限度額 | |
|---|---|---|
| 不動産担保型生活資金 | 土地の評価額の70%程度 | 月30万円以内 |
| 要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 土地と建物の評価額の70%程度 (集合住宅の場合は50%) | 生活扶助額の1.5倍以内 |
申込者が死亡するもしくは限度額に達するまでの期間は、毎月決まった金額を借り入れできます。
最大でも3.0%という低い金利が適用されますので、利息を少なくしたい人は不動産担保型生活資金の利用を検討しましょう。
福祉資金は主に障害者世帯を対象にしている
福祉資金は主に障害者世帯を対象に、介護や通院などに必要なお金を借りられる制度です。
生活福祉資金貸付制度の中で最も適用する範囲が幅広く、以下のように様々な場面で活用できます。
- 福祉用具などの購入費
- 介護や障害サービスを受けるのに必要な費用
- 障害者用の自動車購入費
- 怪我や病気の治療費および療養中の生活費
- 住宅の増改築(バリアフリーなど)や補修費
- 災害を受けたことにより臨時で必要になる経費など
この他にも、事業を営んでいる人が設備や器具などを調達するための生業費も借り入れ対象となっています。
福祉資金の貸付限度額や期間は以下のとおりです。
| 貸付限度額 | 580万円以内 |
|---|---|
| 貸付期間 | 一括で貸し付け |
基本的には一括で借り入れできますが、生活費などの用途に利用する場合は分割になるケースがあります。
限度額は最大580万円であり高額な借り入れにも対応しているため、車椅子の乗り降りに対応した自動車の購入費用などにも充てられます。
借り入れの利用目的に応じて限度額や貸付期間は変わりますので、自分の地域の社会福祉協議会か民生委員に問い合わせてみましょう。
緊急小口資金貸付を利用すれば無利子で10万円まで借りられる
国からお金を借りられる公的融資は、生活福祉資金貸付制度以外にも以下の6種類あります。
| どんな人が申し込めるか | |
|---|---|
| 緊急小口資金貸付 | 生活を送るうえで緊急にお金が必要になった人 |
| 求職者支援資金融資制度 | 失業中で求職している人 |
| 教育一般貸付 | 義務教育以上の子供を持つ保護者 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 20歳未満の子供を扶養しており、配偶者がいない人 |
| 年金担保貸付 | 年金受給者で、年金だけでは生活できない人 |
| 看護師等修学資金 | 学費や授業費の支払いに困っている看護学生 |
中でも緊急小口資金貸付は緊急にお金が必要になった際に無利子で10万円まで借りられる制度のため、できるだけ早く現金が手元に欲しい人にぴったりです。
国の公的融資は審査に3週間ほどかかるのが特徴ですが、緊急小口資金貸付の場合は10日から2週間ほどで融資を受けられます。
具体的には、以下のような緊急性の高い状況の場合に借り入れできます。
- 医療費または介護費の臨時の支払い
- 火災などに被災した際の緊急の生活費
- 年金など公的給付が開始するまでの生活費
- 滞納していた税金や国民保険料などの支払い
- 盗難の被害に遭った際の緊急の生活費
資金を借り入れできるだけではなく自立相談支援機関に今後の生活についての相談に乗ってもらえるため、具体的な生活再建の計画が立てられます。
自立相談支援機関とは?
仕事や生活全般の困りごとについて支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを考えて具体的な支援プランを作成する機関のこと。
自立に向けた支援をおこなってもらえる。
差し迫った支出がある場合は、緊急小口資金貸付を利用して援助を受けましょう。
その他にも、借り入れを必要とする人の状況に応じた制度が導入されています。
求職者支援資金融資制度は仕事を探している人への資金援助
求職者支援資金融資制度は、求職者支援制度を受けている失業者がお金を借りられる制度です。
求職者支援制度とは?
失業保険を受けられない求職者の人に無料で職業訓練を実施し、月額10万円までの職業訓練受講手当を支給する制度。
月10万円の職業訓練受講手当だけでは生活費が不足してしまう場合に、求職者支援資金融資制度を利用すれば追加で融資が受けられます。
求職者支援資金融資制度の貸付限度額は、以下の計算式で算出されます。
| 配偶者や子供、父母がいる場合 | 月額10万円×職業訓練を受講した月数(最大12ヶ月) |
|---|---|
| 単身者 | 月額5万円×職業訓練を受講した月数(最大12ヶ月) |
融資を受けるためには職業訓練に全て出席し、ハローワークの就職支援を受けていることが必須となっています。
融資を受けられても途中でハローワークの就職支援を中断してしまうと、借り入れ残高を一括返済しなければならなくなるため注意してください。
教育一般貸付は超低金利な国の教育ローン
教育一般貸付は、1.66%という超低金利で借り入れできる国の教育ローンです。
国が100%出資して設立された日本政策金融公庫がおこなっており、幅広い用途に利用できます。
教育一般貸付で借り入れできる費用は、以下のとおりです。
- 学校納付金(入学金、授業料、施設設備費など)
- 受験にかかった費用(受験料、受験時の交通費・宿泊費など)
- 在学のため必要となる住居費用(アパート・マンションの敷金・家賃など)
- 教科書代、教材費、パソコン購入費、通学費用、修学旅行費用、学生の国民年金保険料など
つまり学校に通う際に必要となる費用であれば、なんにでも利用できるということです。
以下のように子供の人数ごとに世帯収入の上限が決められており、それよりも下回る世帯が貸し付けの対象となっています。
| 子供の人数 | 世帯収入の上限額(会社員) | 世帯収入の上限額(自営業者) |
|---|---|---|
| 1人 | 790万円 | 590万円 |
| 2人 | 890万円 | 680万円 |
| 3人 | 990万円 | 770万円 |
| 4人 | 1,090万円 | 870万円 |
| 35人 | 1,190万円 | 970万円 |
世帯年収が200万円以下の場合は、金利がさらに低くなったり返済期限が延長されたりといった優遇措置が受けられます。
世帯の状況に応じて相談にも乗ってもらえますので、子供の教育資金に困った際は迷わず相談しましょう。
ひとり親なら母子父子寡婦福祉資金貸付で援助が受けられる
母子父子寡婦福祉資金貸付は、未成年の子供を扶養している配偶者のいない人が生活費の融資を受けられる制度です。
参議院の調査によると、特に母子家庭は生活が苦しいと感じているケースが多いとされています。
このようなひとり親家庭を経済面からサポートするために、以下の12種類の資金が設けられています。
| 内容 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 事業開始資金 | 事業を開始するのに必要な設備の購入資金 | 287万円 |
| 事業継続資金 | 現在の事業を継続するための必要資金 | 144万円 |
| 修学資金 | 高校、大学などに子供を就学させる際の必要資金 | 月額4万8,000円〜9万円 |
| 技能習得資金 | 就職のために必要な技術を習得するための資金 | 月額6万8,000円 46万円(運転免許証の場合) |
| 修業資金 | 事業を開始または就職するための技能を得る際にかかる資金 | 月額6万8,000円 |
| 就職支度資金 | 就職に必要な制服や履物、通勤用自動車などの購入資金 | 10万円 |
| 医療介護資金 | 医療や介護を受けるための必要資金 | 34万円(医療) 50万円(介護) |
| 生活資金 | 失業中の生活を安定させるための生活費 | 月額10万5,000円(一般) 月額14万1,000円(技能) |
| 住宅資金 | 住宅を建設または補修や増築するのに必要な資金 | 150万円 |
| 転宅資金 | 引っ越すために必要な資金 | 26万円 |
| 就学支度資金 | 就学するために必要な制服などの購入資金 | 6万3,100円〜59万円 |
| 結婚資金 | ひとり親家庭の20歳以上の子供が結婚する際に必要な資金 | 30万円 |
国はひとり親に対して積極的な支援をおこなっていますので、困った際は市役所などの地方自治体に問い合わせてみましょう。
年金受給者は年金担保貸付を利用しよう
年金受給者なら、年金担保貸付を利用してお金を借りるという手段があります。
年金担保貸付とは、国民年金または厚生年金保険の年金を担保として独立行政法人福祉医療機構(WAM)から融資を受けられる制度のことです。
以下の3つの条件を、全て満たす金額が限度額となります。
- 10〜200万円以内(ただし生活費の場合は80万円まで)
- 受給している年金(年額)の0.8倍
- 1回あたりの返済額の15倍以内
例えば娘の結婚費用など、冠婚葬祭にかかる費用の場合は最大200万円まで借りられます。
ただし生活費の場合は、最大でも80万円が限度額となりますので気を付けましょう。
窓口は年金を受け取っている金融機関ですが、以下の3ヶ所は取り扱いがありませんので注意が必要です。
- ゆうちょ銀行
- 農協
- 労働金庫
これらの金融機関を利用している場合は、申し込みの際に福祉医療機構に問い合わせてください。
看護師等修学資金は看護学生が学費を借りられる制度
看護師等修学資金は、看護師等養成施設に在学している学生が学費を借りられる制度のことです。
各自治体が指定する200床未満の病院で5年以上継続的に勤務すると支払い義務がなくなり、全額免除が受けられます。
そのため将来自分の住む地域で看護師になることを検討している看護学生には、ぴったりの制度です。
ただし卒業後1ヶ月以内に融資を受けた自治体の病院で働かなかった場合は、返済の義務が生じますので注意しましょう。
個人が国からお金を借りるには市役所か社会福祉協議会で申し込もう
個人が国からお金を借りるための申し込み窓口は、自分の住む市区町村の市役所もしくは社会福祉協議会です。
窓口でお金が必要だという相談をすると、職員から就業状況や生活の状態などのヒアリングを受けます。
聞き込みされた内容で融資が必要だと判断されれば、そのまま申し込み方法の説明を受けるという流れです。
利用目的によっては社会福祉協議会以外が窓口になることもありますが、その際も他の機関を紹介してもらえますので安心してください。
利用する制度ごとの申し込み窓口を、以下にまとめました。
国の個人向け融資制度の申し込み窓口
| 生活福祉資金貸付制度 | 社会福祉協議会 |
|---|---|
| 緊急小口資金貸付 | 社会福祉協議会 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付 | 社会福祉協議会 |
| 教育一般貸付 | 日本政策金融公庫 |
| 求職者支援資金融資制度 | ハローワーク |
| 年金担保貸付 | 独立行政法人福祉医療機構(WAM) |
| 看護師等修学資金 | 自分の通っている看護学校 |
社会福祉協議会は全ての市区町村に必ず設置されており、低金利での貸し付けや各種助成金の提供など多様なサービスをおこなっています。
生活における相談窓口も常設されていますので、いつでも悩みを聞いてもらえます。
金銭的な問題が起こってどこに相談したらいいかわからなくなった場合は、社会福祉協議会を訪ねましょう。
公的融資を受けるためには本人確認書類や住民票が必須
社会福祉協議会に相談し国の公的融資へ申し込むことが決まったら、必要書類を用意しましょう。
基本的な必要書類は、以下のとおりです。
- 借り入れ申込書
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
- 健康保険証
- 家族構成がわかる書類(住民票など)
- 連帯保証人の収入証明
- 自立に向けた計画書
- 個人情報の提供に関する同意書
その他にも申し込む制度によって、必要書類が追加されるケースがあります。
例えば住宅入居費に申し込む場合は、入居する住宅の不動産賃貸契約書などが合わせて必要です。
申し込みの際に社会福祉協議会の担当者から詳しく説明を受けますので、指示に従いましょう。
借り入れまでは2週間が目安で即日では借りられない
国の公的融資は即日融資には対応していないため、融資を受けるまでに2週間はかかります。
公的融資の財源は国民の税金であり、貸し付けをする際は慎重に審査をおこなう必要があるからです。
そのため決定的に生活が困窮してしまう前に、早めに相談に行くことが重要になってきます。
すぐにお金が必要だという場合は、担当者に理由を説明すれば考慮して優先的に審査してもらえる可能性があります。
借り入れまでの流れを簡単な4ステップで解説
借り入れまでの流れを知っておけば、必要なタイミングに融資が間に合わなかったという失敗をなくすことができます。
申し込みから融資までの流れは、以下のとおりです。
STEP1 社会福祉協議会に相談
自分の悩みについて窓口で相談し、職員からの質問に答えます。 どの制度に申し込むべきかが職員によって判断され、その後の手続きについて詳しい説明を受けます。
STEP2 申し込み
借り入れ申込書と必要書類を、社会福祉協議会に提出します。
STEP3 審査
市区町村から都道府県の社会福祉協議会に申し込み書類が送られ、審査がおこなわれます。 審査にはおよそ2週間ほどかかり、貸付決定通知書または不承認通知書が本人に送付されます。
STEP4 融資
社会福祉協議会に規定の借用書を提出し、受理されると融資がおこなわれます。
手順を把握し、自分が必要とするタイミングに借り入れを間に合わせましょう。
決められた償還期間までに返済しないと遅延損害金が請求される
公的融資は制度ごとに償還期間(返済期限)が定められており、期間内に返済しなければなりません。
返済を無断で滞納すると、遅延損害金として10.0%近い金利が上乗せされるので注意してください。
ただし止むを得ない事情があって償還が困難な際は、返済期限を延長してもらえるケースもあります。
返済機関を延長してもらえる旨については、京都府社会福祉協議会のホームページに記載されています。
つまり所定の手続きを取れば、正式に返済を免除してもらえる可能性があるということです。
災害などの被害に遭って返済できなくなったら、必ず担当者に相談するようにしましょう。
返済方法は口座からの自動引き落としが採用されている
公的融資の返済方法には、基本的に口座引き落としが採用されています。
決まった日付に自動引き落としされるため、うっかり忘れて滞納してしまうミスを防げます。
国からの融資とはいえ滞納を繰り返すと受給を打ち切られてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
引き落とし口座には、余裕をもって現金を用意しておくように心がけましょう。

コメントを残す